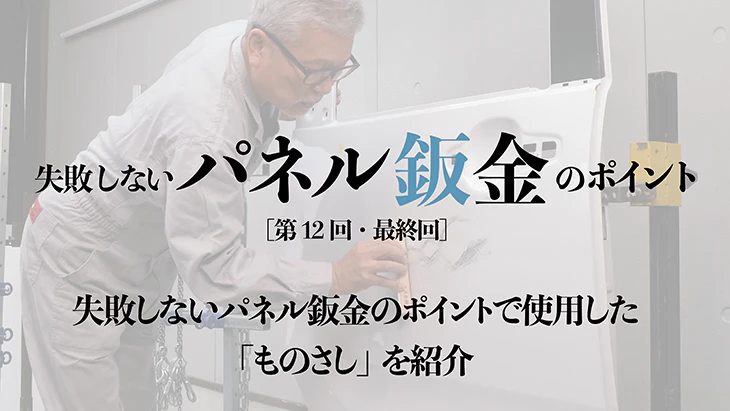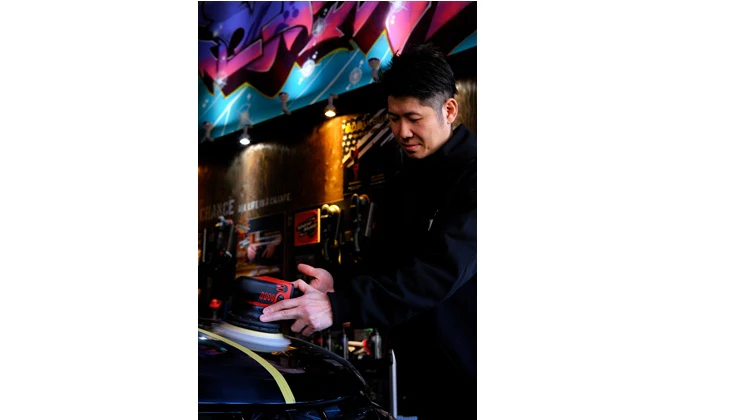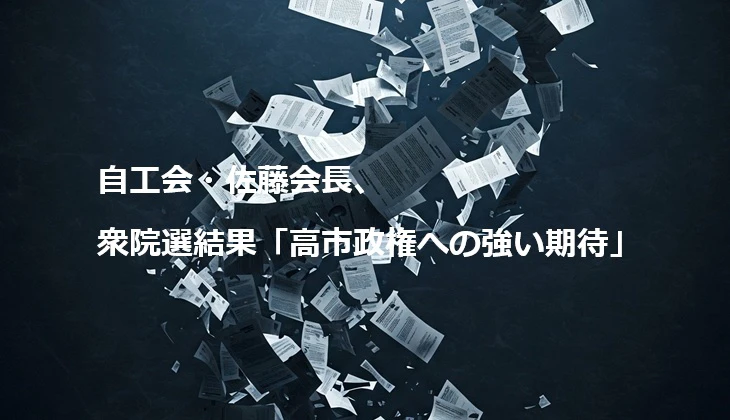JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
自動車業界の動・静脈企業が連携し、BlueRebirth協議会を設立
ELVの自動精緻解体を起点とした「Car to Car」資源循環社会の実現を目指す
2025/09/08
2025年6月、デンソー、東レ、野村総合研究所、本田技研工業、マテック、リバーの6社が発起人となり、BlueRebirth協議会(https://www.bluerebirth.jp)を設立した。同協議会は、使用済み自動車(ELV)の自動精緻解体を起点として質の高い再生原料を大量に抽出し、それをリサイクルすることで環境価値の高い自動車に生まれ変わらせる「Car-to-Car動静脈融合バリューチェーン」の社会実装を目標に、3年間の時限組織として活動する計画である。
実証実験を通じて自動解体の実用性と利点を確認
同協議会の原点は、環境省の事業として2024年3月から約1年間かけて行われた技術実証実験にある。同実験には自動車業界の動脈(製造・販売)と静脈(解体・リサイクル)にかかわる36の企業・機関が参画し、ELVの自動解体プロセス及び抽出した各種素材の高純度化・再資源化プロセスの技術実証、再生原料から製造した部品の評価などを行った。
自動解体プロセスの開発では、まず熟練作業者が10種類の部品を手で解体し、その動作を手術支援ロボットを応用した特殊な装置でデータ化。その作業動作データをAIなどで最適化し、産業用ロボットに再現させ、部品の自動解体が可能であることを実証した。併せて、解体した各部品から単一材料へ分離させる技術や再資源化処理の検証、再生原料から製造した部品(11種類)の性能評価などを行った。それらの実証実験の結果、いくつかの課題は見られたものの、自動解体による再資源化の実用性と利点を確認。また、従来の解体手法に比べ、自動解体は温室効果ガス排出量の削減効果があることも明らかとなった。
バリューチェーンの社会実装で静脈・動脈業界双方の課題解決につなげる
実証実験の報告書では、自動解体プロセスの社会実装に向けたロードマップなども示されている。「これだけの動・静脈のプレイヤーが一堂に会する取り組みは、世界的に見ても稀。この灯を絶やさず、本気で社会実装を目指す人たちの受け皿として、協議会を設立した」(広報・ブランディング分科会・奥田英樹会長=デンソー・サーキュラーエコノミー事業開発部長)。
Car to Carの資源循環を確立するためには、製造側の要求品質に応える再生原料が必要であり、再生原料の品質を高めるためにはELVの精緻解体が求められる。しかし、人の手で解体する従来の手法で精緻に素材を分別しようとすると、工数が大きくなり、経済合理性の確保が難しかった。自動車解体事業を展開するリバーから協議会へ参加する同分科会・平野幹尚副会長(リバー・事業本部事業統括部サーキュラーエコノミー課長)は、「自動車リサイクル業界においても、人材不足は深刻な課題。ELV解体の自動化は、我々の業界の事業継続性という観点からも不可欠だと認識している。さらに自動精緻解体システムは、これまでの解体手法では難しかった再生原料の高品質化を可能とし、“Car to Car”を実現するための非常に優れた取り組みだと考えている」と述べ、静脈側の企業においても自動精緻解体システムの実現によるメリットは大きいとの認識を示す。
自動精緻解体システムでは、自動車の分断及び解体、部品の分解、素材ごとの分離までの全工程の自動化を目指す。併せて、各種車両に柔軟に対応できる解体プログラムの開発及びシステムの効率化に取り組む。さらに、同システムで解体・再資源化された素材が何からどのように作られたかなどのデータを記録・共有することで、製造側の要求に応える品質を可視化する計画。データを共有する仕組みはすでに完成しており、今後は記録する内容について議論を進める。
「日本は資源の少ない国。使い終わった車両を輸出し続ければ、いずれ再生原料までも輸入に頼ることになりかねない。自動精緻解体システムの社会実装によって、ELVが適正な価格で買い取られるような市場を実現したいと考えている。自動車アフターマーケットに携わる皆様には、国内で資源循環することの意義について理解いただくとともに、その実現に向けて協力をお願いしたい」(奥田会長)。
広報・ブランディング分科会・奥田英樹会長(左、デンソー・サーキュラーエコノミー事業開発部長)、同・平野幹尚副会長(リバー・事業本部事業統括部サーキュラーエコノミー課長)