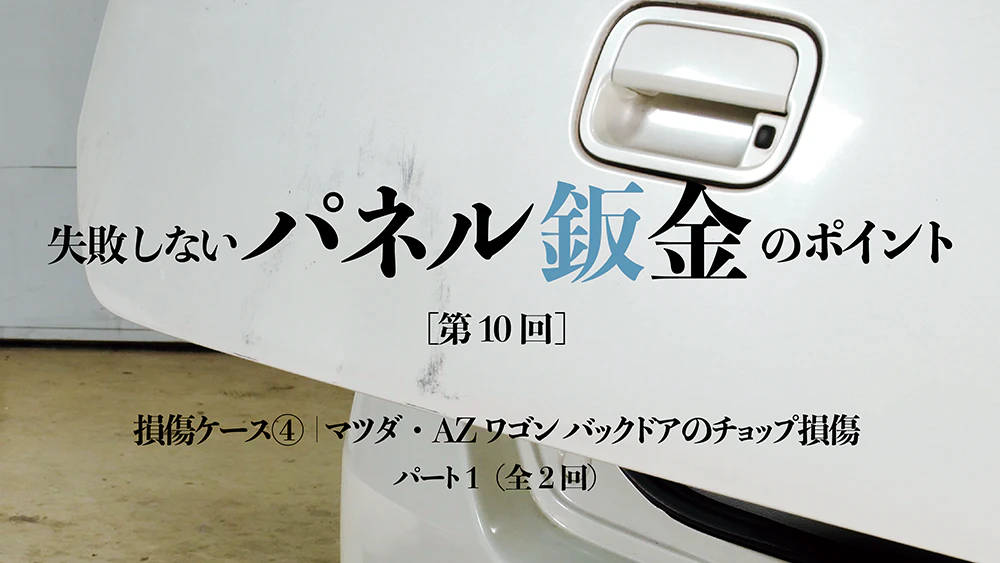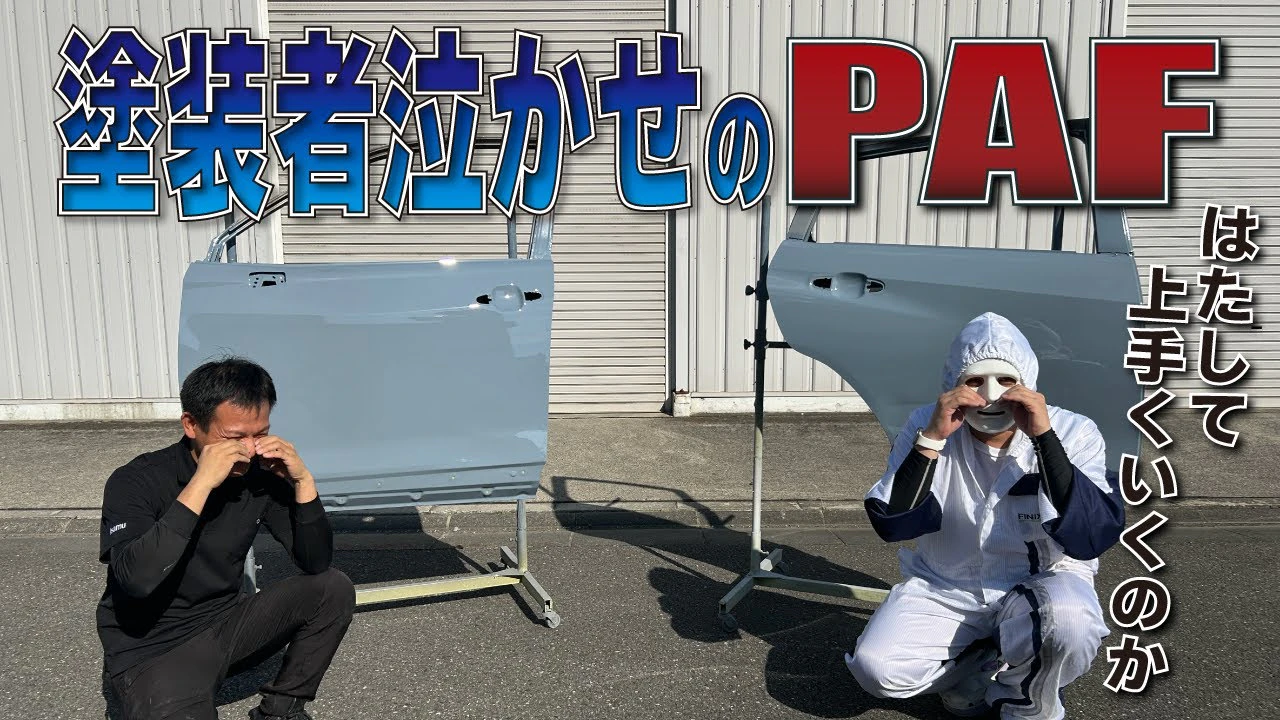JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
「車体整備事業者による適切な価格交渉を 促進するための指針」策定の経緯と目的
~国交省が車体整備事業者に期待すること
2025/04/09
国土交通省は3月4日、「車体整備事業者による適切な価格交渉を促進するための指針」(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000334.html)を公表した。
同省物流・自動車局自動車整備課整備事業指導官の村井章展氏に、指針策定に至った経緯と目的、これを受けて車体整備事業者に期待することを聞いた。
ーー指針を策定した経緯と目的について
内閣官房と公正取引委員会が、2023年11月29日に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表し、政府全体として労務費を価格に転嫁していく方針を示した。指針と併せて公表された資料を見ると、労務費の転嫁率が最も低い業種は自動車整備業だった。この時の調査はBtoBの取引のみを対象としており、車体を含めた自動車整備工場において、取引先企業に対する価格転嫁が課題になっていることが明らかになった。
また、この指針の公表時期に前後して、事故車修理における経費の価格転嫁が思うようにいかないという声が多く届くようになった。さらに2024年3月には、日本自動車車体整備協同組合連合会が損害保険会社に対して工賃単価の引き上げに関する団体協約を求める交渉を開始した。
企業同士の価格交渉は民と民の話なので、これまで行政としてあまり踏み込んでこなかった。しかし今回、労務費の価格転嫁に向けた政府全体の動き、そして業界内における危機感や機運を受けて、車体整備工場による価格交渉を促進することが必要だと考えた。
ーー総額値引きについて、「価格の透明性・公平性に疑義を呈されかねない」とあるが、工場側の取り組みだけでは解消が難しい課題だと感じる
損害保険会社からの要求を受けて、特に理由なく総額値引きしているケースも多いのではないか。総額から理由のない値引きをしてしまうと、そもそも最初の見積りがおかしかったのではないか、という議論になりかねない。
これらの値引きは業界内で商慣行として行われているので、指針の中では「行わないこと」とまでは書かなかった。しかし、ビッグモーターの問題を受けて過剰請求に対する疑いが持たれやすい状況下において、最後に根拠のない総額値引きをすることは、透明性・公平性を疑われかねない行為だと車体整備事業者に認識してほしいと考え、指針に示している。
ーー代車費用の支払いについてなど、具体的な項目も挙げられていた
窓口に寄せられる情報では、損害保険会社のアジャスターから「無過失でなければレンタカー代が出ない」と説明を受けたという声が多いが、ほとんどの自動車保険の約款には、そのような内容は書かれていない。車体整備事業者が損害保険のルールを理解すれば、代車費用の請求漏れが防げるのではないかという考えから記載した。
ーー修理工場が契約の確認を求めても、第三者には開示できないと、損害保険会社から断られるケースもあるようだ
そのような場合は、カーオーナー経由で確認すべきだろう。
すべてをエンドユーザーに振るとユーザーの負担が増えてしまうし、ユーザーとしては保険金で全部済ませてほしいというのが正直なところだと思う。しかし、完全に損害保険会社と工場に任せ切りにしてしまうと、結果としてカーオーナーの意図と異なってしまうケースもあるだろう。カーオーナーにも、ある程度の当事者意識は持ってもらわないといけないと考えている。
工賃単価が上がらない問題について、車体整備事業者は損害保険会社に原因があると主張するが、三者三様に直さなければいけないところがある。車体整備工場は自分で請求の根拠を説明できる能力を身に付け、透明性を疑われないようにしなければならないし、損害保険会社は車体整備事業者とていねいに対話をしなければならないし、カーオーナーは当事者意識を持たなければならない。
ーー最近は、産業廃棄物処理費用の請求が認められないという声も多い
産業廃棄物処理に関する費用についての意見は、情報提供窓口にも多く寄せられる。産業廃棄物の処理に費用が発生しているのであれば、当然請求すべきである。交渉した結果、請求が認められないこともあると思うが、その時には“0円”としっかり書いておくべきである。費用項目自体をなくすべきではない。
費用請求しないという条件を飲み込んだのであれば、“0円”と書いておく。それらの記録がたまると、損害保険会社との次の交渉に使えるかもしれない。
ーー産業廃棄物処理に関する費用について、工場経費に含まれているという見解を示すアジャスターも多いと聞く
そのような声も届いている。しかし、工場経費に含まれているというのであれば、そもそもどの程度含まれていて、費用上昇はどのように反映されているのか、という議論があるべきだ。実際に、そのような議論をしている事業場の話も聞いている。
公正取引員会等が示した指針は労務費の転嫁に関する内容だが、今回国交省が策定した指針は労務費に限らず、発生した費用はしっかり交渉するべき、という趣旨である。もちろん相手がある交渉なので、すべてが認められることはないと思うが、相手の要求をすべて飲む必要もない。
今回の問題については、損害保険会社側も真摯に議論に応じている。車体整備事業者と損害保険会社が共存共栄できるように、現場の交渉が円滑に進む方法を一緒に考えてきた。
車体整備事業者においては、自社の責任と考えによる見積りの作成、そしてその内容について論理に基づいた説明ができる体制をしっかりと整えていただきたい。
ーー損害保険会社との価格交渉に関する情報提供窓口に寄せられた情報は、どのようなことに活用されるのか
まず指針内の注記で明言している通り、個別の問題に対応することはない。国交省には、損害保険会社に対して行政指導などを行う権限はない。
その上で、提供を受けた情報の活用方法は、大きく分けて2つある。1つ目は、今回の指針などのような政策への活用。もう1つは、集めた情報を損害保険会社ごとに振り分け、情報提供者が特定されない形に加工した上で、それぞれの損害保険会社と対話をするために用いていく。この損害保険会社との対話は、国交省だけではなく金融庁、公正取引委員会、中小企業庁の4省庁で対応する。
価格転嫁をする上で望ましい交渉の在り方が労務費転嫁に関する指針で示されており、我々もそれを参考に今回の指針を策定した。また、今年に入り日本損害保険協会も車体整備事業者との価格交渉に関するガイドラインを作成している。それらと照らし合わせて、我々の窓口に寄せられた情報にあるような対応は適切だったのか、ということを各損害保険会社と対話していく。その対話を受けて、損害保険会社が改善すべきところについては、改善してもらえると考えている。
価格交渉については、指針を出したから直ちに改善されるような課題ではないと認識しており、PDCAを回して取り組むことが大事だと考えている。車体整備事業者と損害保険会社との価格交渉の実態について、国交省は継続して確認していく。
ーー本指針を受けた車体整備業界及び事業者に期待すること
まずは、しっかりと価格交渉ができる体制を整えていただきたい。
車体整備工場においては、自社で見積書を作成していないケースが散見される。価格交渉をするためには、まず自分で見積りを考え、請求できるようになる必要がある。そのためには工賃単価の算出方法だけではなく、指数の考え方も理解しなければならない。現状においても、それらを理解した上で損害保険会社との交渉に臨み、工賃単価の値上げができている事業者もいる。
昨年7月から、保険修理の価格交渉に関する車体整備事業者からの情報提供窓口を設置したところ、様々な声が寄せられている。提供された情報の事実認定をしているわけではないが、損害保険会社からひどい条件を要求され、それをそのまま認めざるを得ないという意見も少なくなかった。
そのような要求を受けた時、車体整備事業者側はしっかりと自分の言葉で反論できるようにならなければならない。明確な根拠を示し、料金が適正であることを論理的に説明したにもかかわらず、相手側が地域相場で決まっているなど論理性を欠いた説明で押し切ろうとした時になって初めて「相手側がおかしい」と指摘することができる。
また、業界団体などにおいては、すべての車体整備事業者がそのような対応ができるように、業界全体に向けた教育を進めていただきたい。車体整備業界においては、団体などに所属していない事業者も少なくない。団体に入るかどうかはもちろん各事業者の自由であるが、そのような事業者を含めて業界全体がレベルアップしていかなければ、価格交渉ができない事業者が残ってしまう。独禁法には注意しなければならないが、業界全体で勉強して、全事業者がしっかりと交渉できる体制を整えてほしい。
国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課 整備事業指導官・村井 章展 氏