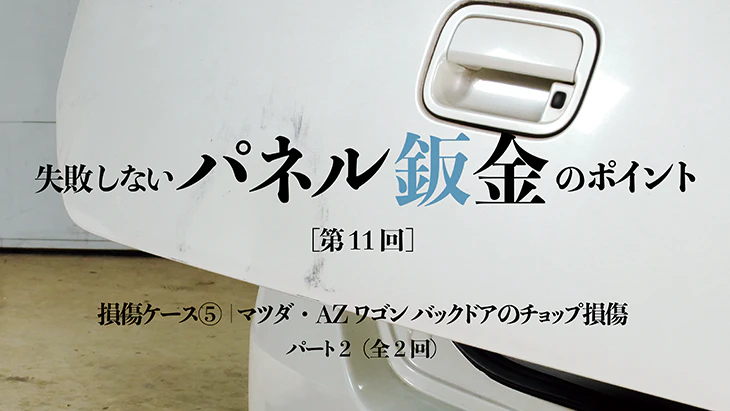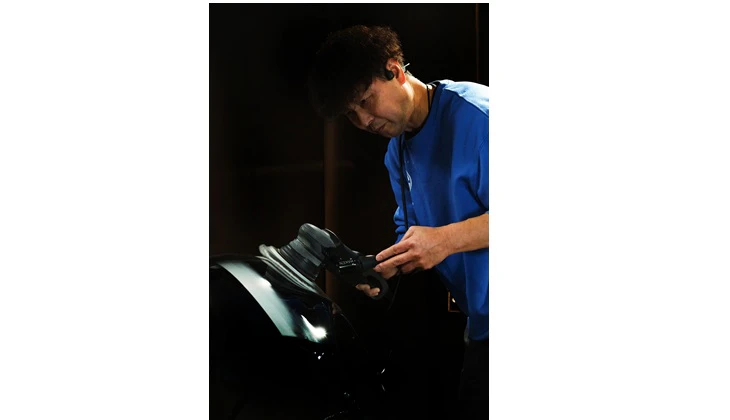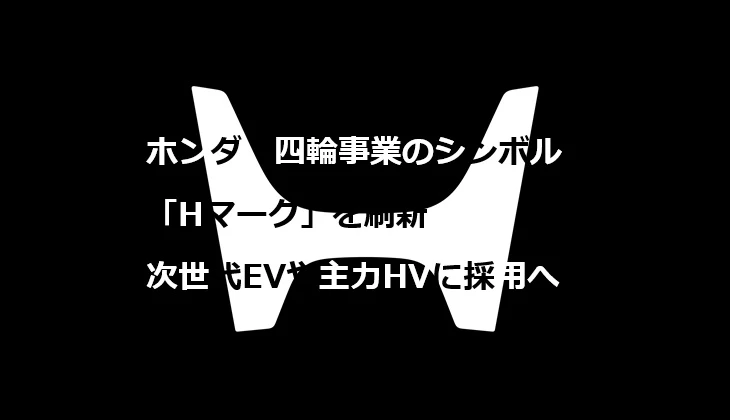JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
代車費用を損害保険会社に請求するつもりで、貸し出す前に考えるべき事柄
その代車の貸し出し、相当性はありますか?まずは損害保険会社と話し合いを
2025/05/10
記事の内容を要約すると…
- 国土交通省が車体整備事業者向けに代車費用の新たな指針を発表: これまで不明確だった自動車修理期間中の代車費用について、保険会社が過失割合のみを理由に請求を拒否する行為に一石を投じる内容となっています。
- 代車費用の支払いは「相当因果関係」が鍵: 指針では、代車費用(有償の「わ」「れ」ナンバーに限る)の保険金支払いは個別判断が原則としつつ、事故と代車利用の間に合理的な関連性(代車の必要性、車種、期間の妥当性)が認められれば、過失割合が100:0でなくても損害賠償の対象となる場合が多いと明記されています。
- 保険会社との連携がより重要に: 指針は、過失割合のみでの門前払いを否定する一方で、「相当因果関係」の検討は依然重要です。車体整備事業者は、安易な代車提供ではなく、事前に保険会社と連携し費用について確認することで、後のトラブルを避けることを推奨しています。
<本文>
国土交通省が3月に発表した『車体整備事業者による適切な価格交渉を推進するための指針』の中で、これまで不明確であった代車費用の取り扱いについて新たな方向性が示され、車体整備事業者の間で大きな注目を集めている。
これまで、車体整備事業者が修理期間中の代車費用を請求しようとした際、事故に過失割合があると、それを理由に一蹴されるなど、正当とみられる請求が通らないケースが散見された。しかし、今回の指針では、損害賠償における代車費用の支払いに関する考え方が明確に示され、こうした状況に一石を投じるものと期待されている。
指針では、代車費用(有償での貸与が可能な「わ」、「れ」ナンバーに限る)の保険金支払いについて、個々の保険契約の内容や事故の過失割合、保険契約者の意向等を踏まえた個別判断が原則であることが強調された。特に注目すべきは、「依頼者と事故の相手方の責任割合が『0:100』でなければ、代車費用に対する損害賠償金(対物賠償保険金)が支払われないと誤解している者がある」と指摘し、「約款上、『0:100』でなくとも、事故との相当因果関係(車格・日額・期間)が認められる代車費用については、過失割合に応じた損害賠償金支払いの対象となるとされているものが多い」と明記された点だ。
相当因果関係の条件を満たしていながら、過失割合を理由に代車費用の請求を諦めてきた車体整備事業者にとって、この指針は朗報と言えるだろう。
■代車費用請求の要点 「相当因果関係」が鍵
実際に代車費用の支払いを検討する際には、「相当因果関係」という考え方が重要となる。これは、法律用語で、発生した損害が、その行為から 自然に(社会通念上逸脱しない範囲であるか)生じると認められるかどうかを判断する。交通事故における代車費用の場合、事故によって車両が使用できなくなった期間に代替車両を用意することが社会通念上、当然であるかが問われることになる。
代車費用の相当性を判断する場合、おもに以下の3つの要素が検討される。
1.代車の必要性
被害車両の所有状況:被害者が他に利用できる車両を所有している場合、代車の必要性は低く判断される可能性がある。ただし、家族構成やそれぞれの車両の使用状況によっては、他の車両があっても代車が必要と認められるケースもある。
被害車両の使用用途:通勤、通院、業務など、日常生活や社会生活を送る上で被害車両が不可欠であったかどうかは重要な要素となる。単なる趣味やレジャー目的での使用であれば、必要性が低いと判断されることもある。
代替手段の有無:公共交通機関が充実している地域や、タクシーなどの代替手段が容易に利用できる環境であれば、必ずしも代車が必要とは言えない場合がある。しかし、時間的な制約や身体的な状況によっては、公共交通機関の利用が困難な場合もありその場合は、代車を認める方向で検討される要素となる。
2.代車の車格
被害車両の仕様用途:単に大きさだけでなく、例えば仕事で特殊な機材を運搬するために特定のサイズの車両を使用していた場合、代車にも同程度の積載能力が求められることがある。
被害車両のグレード:一般的には、被害車両と同程度または同クラスの車格が相当とされる。不必要に高級な代車を利用した場合、その差額は自己負担となる可能性が高い。
合理的な選択:入手可能な代車の状況によっては、多少車格が異なる場合でも、合理的な範囲であれば認められることがある。
3.使用期間の妥当性
修理期間:修理が可能であれば、その合理的な修理期間が代車の利用期間の上限となる。修理期間が不当に長期化した場合、その延長期間の代車費用は認められないことがある。
買い替え期間:車両が全損となり買い替えが必要な場合、合理的な買い替えに必要な期間が代車の利用期間となる。買い替えの意思決定や手続きを速やかに行うことが求められる。
これらの要素を総合的に判断し、損害保険会社は代車費用の支払い可否、そしてその金額を決定する。
■保険会社との連携が不可欠
今回の指針で、過失割合のみを理由とした代車費用の門前払いは否定されたものの、上記のような「相当因果関係」の検討は依然として重要となる。車体整備事業者は、安易に代車を提供し請求するのではなく、事前に損害保険会社と連携し、費用の支払いについて確認を得ることが、後のトラブルを避ける上で賢明な判断と言えるだろう。
今回の指針が、車体整備事業者と損害保険会社との間で、より建設的で透明性の高い価格交渉を促進する一助となることが期待される。