 JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
サイバーセキュリティと整備性の狭間で揺れる自動車業界 汎用スキャンツールの是非
汎用スキャンツール機能拡張が期待される 現場の声届くか
2025/05/24
自動車の電子制御化とサイバーセキュリティ対策の進展が、自動車整備業界に新たな課題を突きつけている。特に、一般の整備工場や車体整備工場が直面する費用負担と技術的障壁は深刻であり、その根底には自動車メーカー側の思惑が透けて見える。この問題は、2025年3月21日に開催された第29回自動車整備技術の高度化検討会(国土交通省主催)でも主要な議題として議論された。
同検討会は、自動車の安全・環境性能向上に伴う電子制御新技術の普及を受け、その性能維持のための適切な点検整備の重要性を認識 。汎用スキャンツールの活用促進や整備要員の技能向上といった人材育成を課題として、平成23年度より開催されている。
汎用スキャンツール、機能拡張が急務
自動車の電子的故障診断に不可欠なスキャンツールは、サイバーセキュリティ強化の潮流の中でその機能が大きく制限されつつある 。2022年7月の法改正により、自動車メーカーは製造・販売時だけでなく、廃車に至るまで車両の瑕疵なき状態を求められるようになった。このため、特に自動ブレーキシステムなどの基幹プログラム保護のため、セキュリティゲートウェイの設置など対策を強化している 。結果として、DTC(ダイアグノスティック トラブル コード)の読み出し・消去、制御用コンピューターの再学習や登録作業といった日常的な整備が、自動車メーカー純正品以外の汎用スキャンツールでは行えないケースが顕在化している。
整備業界からは、オイル交換時期の警告表示がサイバーセキュリティとの関係で消去できない事例 や、OBD検査で不適合となった車両の整備に純正スキャンツールが必要となる懸念が示されている 。車体整備業界においては、エーミング作業で純正スキャンツールでも対応できない事例が散見され、ADAS関連部品の交換に至っては汎用スキャンツールが全く役に立たない状況も報告されている。
このような現状に対し、一般の整備工場や車体整備工場の費用的な負担を考慮すれば、汎用スキャンツールの機能拡張は喫緊の課題と認識される。日常的な整備に支障をきたさない程度の性能強化は不可欠だ。
カーメーカーの「本音」と市場の公平性
一方で、カーメーカーが純正スキャンツールを用いた整備を前提とする背景には、盗難や不正改造リスクへの対応という言い分がある 。しかし、その「保護」が結果的に、ディーラー以外の整備工場を締め出すような状況を生み出している現状に対し、業界内からは疑念の声も上がる。
例えば、純正スキャンツールの利用には、作業ごとのサーバー接続費用や高額な初期費用、更新料が発生するケースがある 。加えて、時間と手間のかかる追加認証が求められることも少なくない 。これらの負担は、多数のカーメーカーの車種を扱う一般の整備工場にとっては、大きな設備投資を意味する 。国土交通省は、純正スキャンツールでエイミング作業ができないのは費用の問題や認証の手間であり、実際に作業ができないわけではないのかと問題提起したが、日車協連からは「実際に作業のできないものが一部ある」との切実な声が上がった。
こうした状況を鑑みると、カーメーカーが費用負担や認証の手間を課すことで、ある程度の規模を持つ整備事業者、すなわち自社の系列ディーラーやそれに準ずる工場にのみ整備を許容したいという本音が見え隠れする。これは、道路運送法第57条の2第1項の下位法令にある「要件は合理的かつ非差別的でなければならない」という精神に反する可能性も指摘されている。
今後の議論の行方
現在、汎用スキャンツールの開発情報提供に関する運用ルールの抜本的見直しが検討されており、各団体からは概ね賛同が得られている 。これは、国連規則(UN R155、UN R156)の解釈の範囲内で、自動車メーカーに過度な負担をかけることなく、新スキームを進められるという見解に基づいている。
しかし、サイバーセキュリティ確保と整備業界の公平性の両立は依然として大きな課題である。カーメーカー側は、ソフトウェア改ざんによる実害発生リスクを懸念し、信頼担保のあり方について慎重な姿勢を崩さない。今後、具体的な車種や作業を特定した困りごと調査を通じて、より詳細な実態把握と、カーメーカー、整備業界、国土交通省が一体となった議論が求められる。自動車の高度化が加速するなか、全ての車両が適切に整備される環境をいかに構築するかだが、サイバーセキュリティの担保と整備の利便性の調和をどこに置くのか、議論の行く末を見守りたい。
<文・石芳賢和>
あなたにおすすめの記事
-
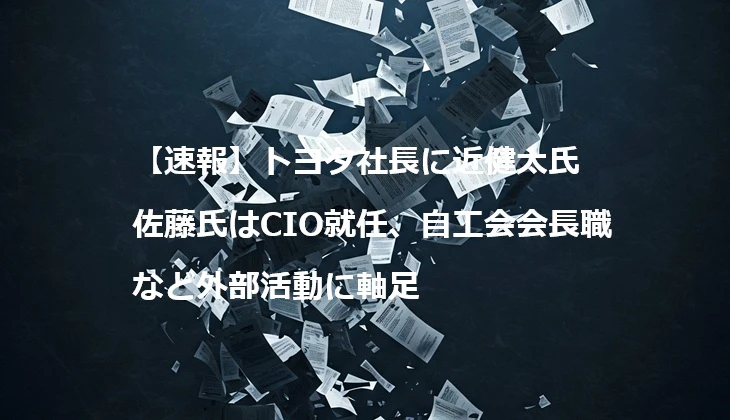
【速報】トヨタ社長に近健太氏 佐藤氏はCIO就任、自工会会長職など外部活動に軸足
2026/02/06
-
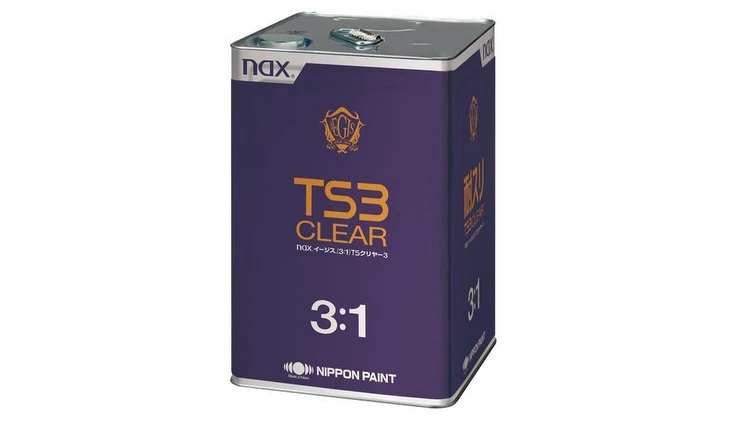
日本ペイント naxイージス(3:1)TSクリヤー3
2026/02/06
-
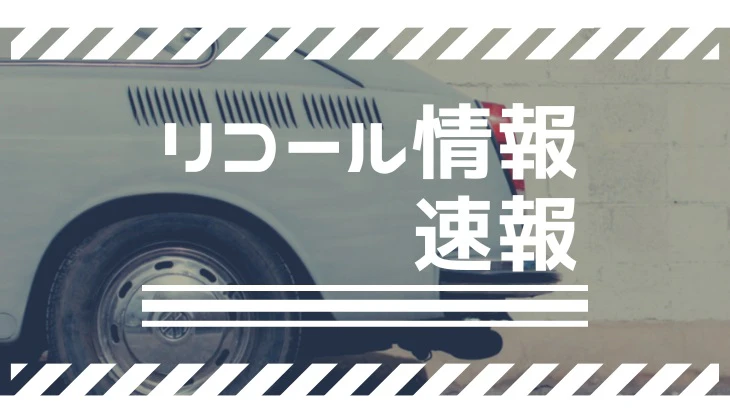
スバル、レヴォーグ(VN5、VNH)・WRX(VBH)を756台リコール パワステ不具合で操作力増大の恐れ
2026/02/06
-
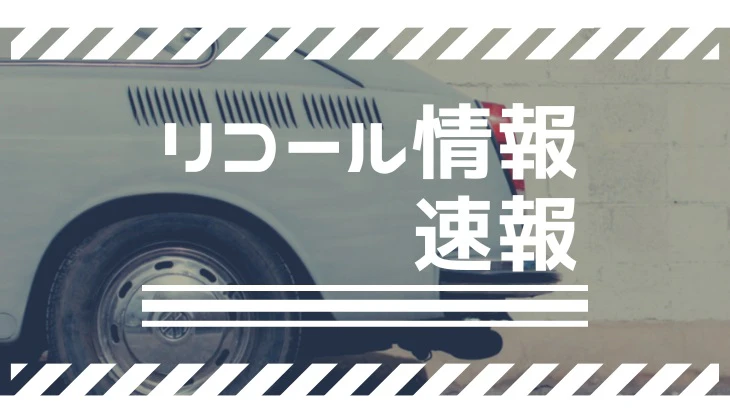
スズキ、ジムニー(JB64W)1211台をリコール エンジン始動不能のおそれ
2026/02/06
-
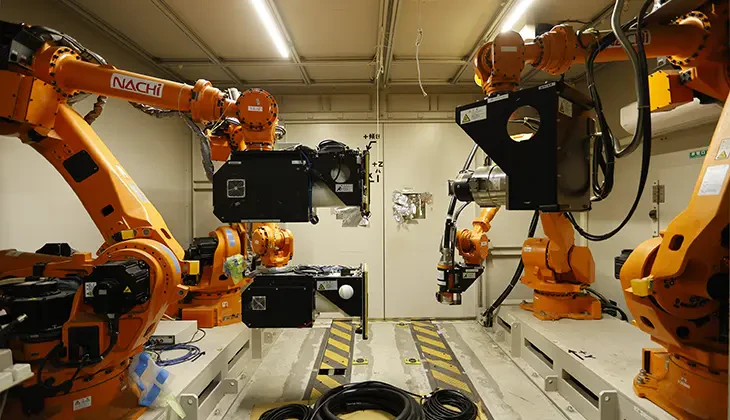
日産、大阪大学接合科学研究所と「日産自動車 溶接・接合共同研究部門」を設立
2026/02/06
-

吉崎鈑金、福井県内初のテスラ認定ボディショップに。日本国内で50社目の認定取得
2026/02/06


























