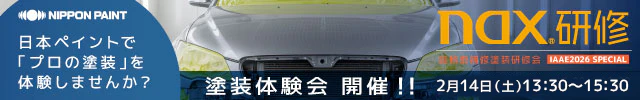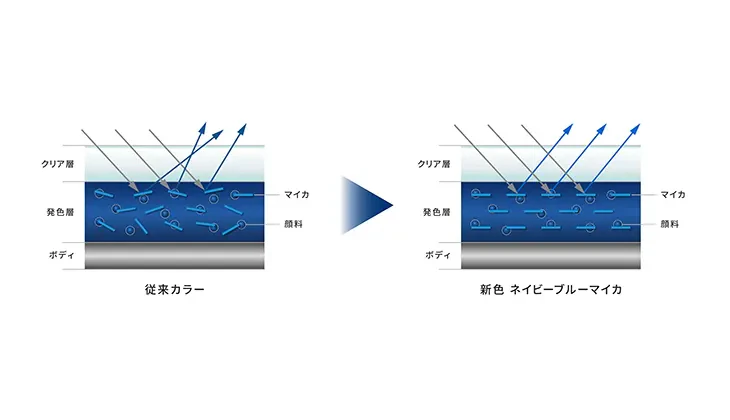JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
塗装材料費率はなぜ嫌われたのか?
2025/11/01
事故車修理の見積もりにおける「塗装材料費率」は、車体整備事業者にとって不満の対象となってきた。車両の塗装工賃総額を基に、保険会社と事業者が合意した割合で材料費を算出するこの方式は、なぜ現場で歓迎されないのか。その原因は、業界の「塗装材料費の基準」が揺らいだ1997年以降の経緯にある。
塗装材料費の「具体的な数値」が消えた日
かつて、補修塗装指数を公表していた自研センターは、パネルごとに具体的な塗装材料費の金額を記していた。しかし、この金額は大口購買が可能な自研センターの調達価格を参考に算出されており、零細企業が多数を占める車体整備事業者の実態と乖離しているという不満が噴出した。
この反発を受け、1997年以降、自研センターは具体的な材料費の数値を指数から撤廃した。これにより、一旦は適正な塗装材料費の交渉に向かうものと見られた。
システムに組み込まれた「既定値」の呪縛
ところが、基準が失われた影響を鑑みて、当時の日本アウダテックス(現コグニビジョン)が動いた。同社は、塗装指数の改訂に伴い、1996年度版の指数テーブルを基に材料代の割合を試算し直し、自社の見積もりシステムに組み込んだ。
その結果、協定の現場で保険会社側が使う事実上の標準値として扱われることとなり、この「試算された材料費率」が交渉の前提条件となってしまった。
事業者が指摘し、一度は撤廃された古い基準を基にした数値が、形を変えて業界の共通認識として利用され続けたこと、そしてその数値の交渉が「没交渉」の時期を経て柔軟性に欠けた運用をされたことが、整備事業者側に「押し付けられた基準」という不満を残す結果となった。
特殊塗料以外は工賃単価に組み込むのはどうか?
こうした構造的な不満の解消には、抜本的な見直しが必要ではないか。
筆者の私見だが、特殊な顔料やクリヤーを除き、一般的な塗装材料費は、パテ代などを含め工場の原価に組み込み、工賃単価の中で回収することを検討してはどうか。
これにより、これまで計上しにくかった調色失敗や塗料の消費期限切れといったコストも、工賃として回収可能になる。また、修理案件ごとに材料費率を巡る協定の手間をなくし、効率化に繋がる。
塗装材料費率は、裁判などで損害認定額を算出する際の「目安」や、車体整備事業者を介さない認定払い時のツールとして運用する。双方に良い思い出がないこの運用を続けるよりも、新たなルールへ移行することが、業界全体の生産性向上と公平性の確保に繋がると筆者は考えるが、皆さんの見解はいかがだろうか。
<文・石芳賢和>