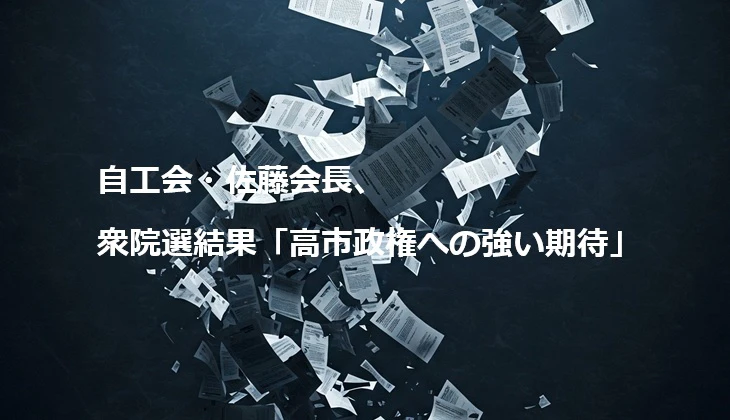JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
[特集]地域連携のススメ(8)~事例:メカトロクラブZENSHIN
整備技術力と組織力を両輪として大阪の整備業界を盛り上げていく
2025/08/04
自動車整備技術だけでなく、組織力も備えたエキスパート集団を目指すメカトロクラブZENSHIN(中原智会長)。1995年にアサダ自動車商会・浅田純一社長(現同会・副会長)が前身となる団体を発足させたが、一度は活動を休止。その後、大阪自動車青年会議所で会長を務め、組織論に精通した中原氏を2021年に会長として迎え、現在のメカトロクラブZENSHINとして再スタートを切った。2025年で5年目を迎える中原会長に聞いた。
団体として質を維持しながら波及を目指す
1995年に前身団体を設立した背景には、同年の道路運送車両法改正により前車検・後整備が可能となり、事業者ごとの整備品質の差に対する危機感があったと言う。そのため、浅田氏の持つ電子制御装置機器などの整備技術を中心に、故障原因を追求しながらの技術力向上を目指した。ところが、団体組織としてのまとまりは徐々に薄れてしまう。
この反省を活かし、2021 年に再結成した際には、会則を設け会費制の団体とした。「お金を払ってでも整備技術などの情報を取得したい、意欲的な事業者だけを対象に活動している」(中原会長)。また、総会を定期開催し活動内容を議案を通じて明確化することで、各事業者が会員意識を高める取り組みも行っている。
現在の会員数は17 社であるが、会員拡大を急ぐつもりはないと言う。「会員の整備技術力、フロント対応力、経営力を底上げし、高い質を保ちながら足並みを揃えることを優先したい」。大阪府近隣の事業者を含めた組織として活動しているが、将来的には大阪府内に各支部を設け、既存メンバーが各ブロックの主軸となることで活動規模を広げる予定。これにより、大阪地域全体の整備技術力の向上につなげていく。
技術の根幹を学び真のプロフェッショナルに
組織作りだけでなく、高度化する整備技術への対応にもさらに注力している。都市部の整備事業者は、「技術で修理しているのではなく、アッセンブリー交換(チェンジニア)が多いと言われる現状を変えたかった」。地方と比較してより顕著となるこの傾向だが、メカトロクラブZENSHINでは、なぜ部品が潰れているのかを考え、対応する技術を学び直すことに主眼を置く。故障個所に対しアッセンブリー交換だけを顧客に勧めるのではなく、故障診断の原因を把握し、適切な説明と金銭的負担を減らす修理を提案できる修理工場を多く作っていくことが同団体の目標でもある。
講習は、毎月第1土曜日に座学と実習を交えて実施している。EV整備に備えるだけでなく、ウィンドウリペアやデントリペア、協定の仕組みなど、車体修理に関わるアフターマーケット全体の見識を高められるようカリキュラムが組まれている。「適正な技術を適正な価格で提供するのが望ましい。そのためのものさしを、他社と関わることで多角的な視点を持ちつつ、作り上げていきたい」。