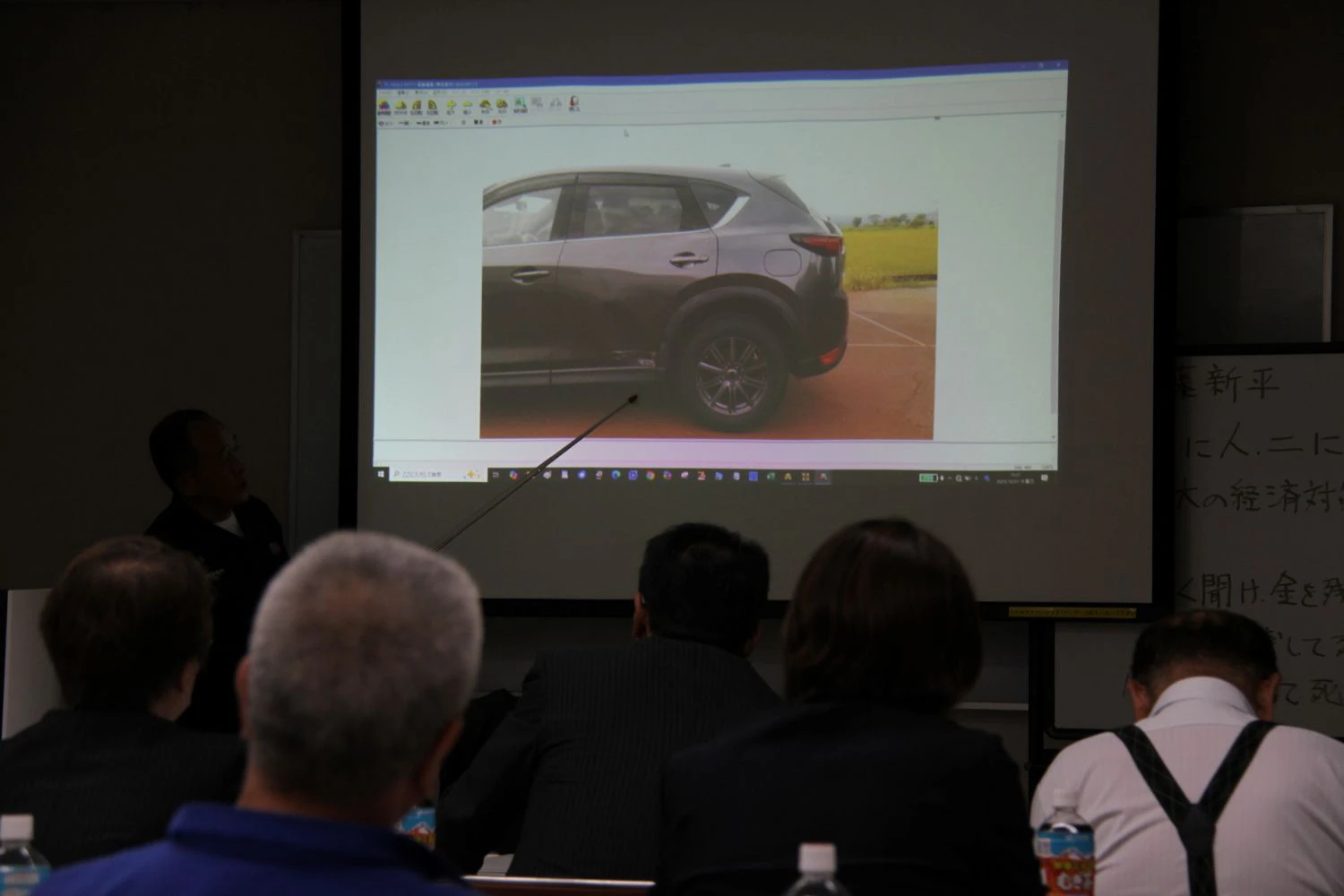JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
新潟県車協・中越支部、 画像伝送セミナーを開催
損保ジャパンから講師を招き、相互理解深める
2025/11/18
新潟県自動車車体整備協同組合・中越支部(井浦康雄支部長)は10月1日、ワークプラザ柏崎(柏崎市)にて、経営セミナーとして「事故修理における画像伝送」をテーマに、写真協定における適切な撮影方法の座学と実技や、業界課題について意見交換を行うセミナーを開催した。第1部ではゲスト講師として招かれた損害保険ジャパン(以下、損保ジャパン)・新潟車両損害調査課の鈴木竜太課長と樋渡勇気氏が写真協定に関する座学を、第2部では井浦支部長が車両撮影を実習、損傷の状態を正確に伝えるためのポイントを解説した。
セミナー風景
顧客のための写真撮影を
第1部の冒頭、損保ジャパン・鈴木氏は画像伝送の取り組みについて、「長らく損保側が修理工場に写真撮影を依頼し、工場側も依頼を受けたから撮影するという一方的な関係が続いてきた。だが国土交通省の発布したガイドラインにより状況は大きく変わった。写真撮影は鈑金塗装の作業工程として、修理と同程度に重要な業務の1つになった」との見解を示した。そして、「写真で事後検証性を残すのは協定のためではなく、顧客のためだ。工場が提供するサービスの一部として、顧客や社会に透明性を示すという視点で撮影する必要がある」と強調した。
損傷写真の好例と悪例の比較解説も行われ、「パネルの交換前後や塗装前後など作業の各段階が分かる写真を残すことで適切な評価につながる。特に塗装中の写真は、マスキングやボカシの範囲がどの程度だったかを確認できる重要な資料になる」など具体的にアドバイス。「損傷は実際に見るのと写真では見え方が違う。分かりにくい損傷はマスキングで囲うなど明示されていたほうが評価がしやすい」と調査側の視点で分かりやすく説明した。
また、実際にあった不正請求事例にも触れ、「不正はごく一部の工場での例だが、BM問題を皮切りに修理工場、そして損保への顧客の信頼が揺らいでいる。損害調査を通して円滑かつ透明性のあるコミュニケーションを行い、工場と損保が互いの信頼関係を深めながら業務を進めることが、最終的に顧客満足につながる」と結んだ。
第1部の冒頭挨拶に立つ損保ジャパン・鈴木竜太氏
写真は全体から細部へ
第2部は井浦支部長による事故車両の撮影実習が行われた。5方向+4方向(1時・5時・7時・11時)撮影や損傷部位の高さに合わせてカメラを構えることなど基本項目を押さえた上で、「単に損傷を写すだけではなく、その損傷がどのような衝突メカニズムで発生したかを読み取れるような撮影が重要だ」と話し、パネル同士のすき間や車高の左右差などのわずかな変化にも注目して撮影することを解説。乗員のケガの状況まで聞き取り、インストルメントパネルやステアリング周りなどを確認して、衝撃で乗員がキャビンのどこに接触したかまで推測、損傷波及の細部まで写真に収めることが精度の高い損傷診断と正確な協定につながると伝えた。
最後はパネルディスカッションが行われ、損保ジャパン側が工賃単価改定や産業廃棄物処理費用などの業界が直面する課題についての質問に回答。率直な意見があり、総じて、修理工場と損保の相互理解が進んだ1日となった。
新潟県車協・中越支部 井浦康雄支部長
あなたにおすすめの記事
-

【ジャパンモビリティショー2025:ホンダ、スズキ】市販化を前提とした手に届きやすいBEVのプロトタイプを披露
2026/01/10
-

【ジャパンモビリティショー2025:トヨタ、ダイハツ】カーオーナー一人ひとりのニーズに寄り添うクルマを多彩なコンセプトカーで提案
2026/01/10
-

【ジャパンモビリティショー2025:センチュリー、レクサス】ブランド化された「センチュリー」のクーペ、群戦略化を示唆した「レクサスLSコンセプト」などを公開
2026/01/10
-
東京オートサロン2026 フォトセレクション
2026/01/09
-
東京オートサロン2026 フォトセレクション
2026/01/09
-
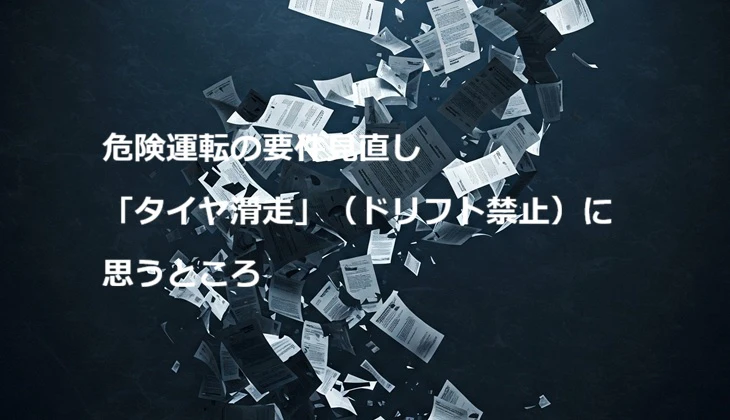
危険運転の要件見直し「タイヤ滑走」(ドリフト禁止)に思うところ
2026/01/09