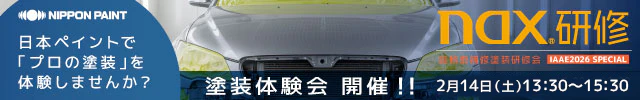JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
【解説】車体整備の技術料、指数対応単価と工賃単価、その違いとは
2025/05/01
先日、日本自動車車体整備協同組合連合会(日車協連)が記者発表を行い、車体整備事業における技術料の考え方について言及した。特に注目されたのは「指数対応単価」と「工賃単価」という二つの言葉だ。いずれも車体整備事業者が1時間あたりの作業に対して得る技術料を示すものだが、その背景には異なる視点が存在する。
■保険会社との協定が生む「指数対応単価」
「指数対応単価」とは、主に損害保険会社との間で協議され決定される、1時間あたりの技術料を指す。多くの協定において、損害保険会社と車体整備事業者の間では、自研センターが定める作業工数、「指数」が用いられるのが一般的。この指数に掛け合わせる技術料の単価を示す言葉として、「指数対応単価」という表現が用いられる。つまり、これは保険会社の立場から見た技術料の捉え方と言えるだろう。
■事業者の視点「工賃単価」
一方、「工賃単価」は、車体整備事業者が自社の作業時間に対して設定する1時間あたりの技術料を示す。車体整備事業者の間では、「指数対応単価」もこの「工賃単価」の一種として捉え、区別せずに語られることも少なくない。
■経営を左右する「レーバーレート」
さらに、関連する言葉として「レーバーレート」が存在する。これは、工場運営にかかる原価に事業者の利益を上乗せし、それを1時間あたりの技術料に換算したものである。車体整備事業者にとって、このレーバーレートは事業を維持するための生命線とも言える。もし実際の技術料がこの数値を下回れば、資金繰りの悪化や赤字経営に繋がりかねない。そのため、多くの事業者は「指数対応単価」や「工賃単価」が、この「レーバーレート」を下回らないように経営努力を行っている。
あなたにおすすめの記事
-
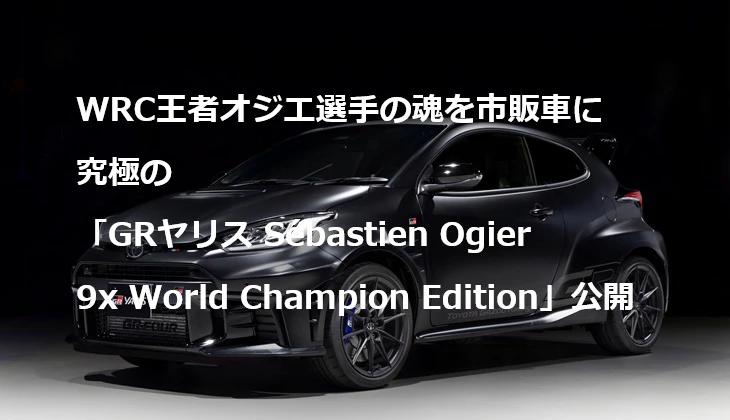
WRC王者オジエ選手の魂を市販車に 究極の「GRヤリス Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」公開
2026/01/24
-
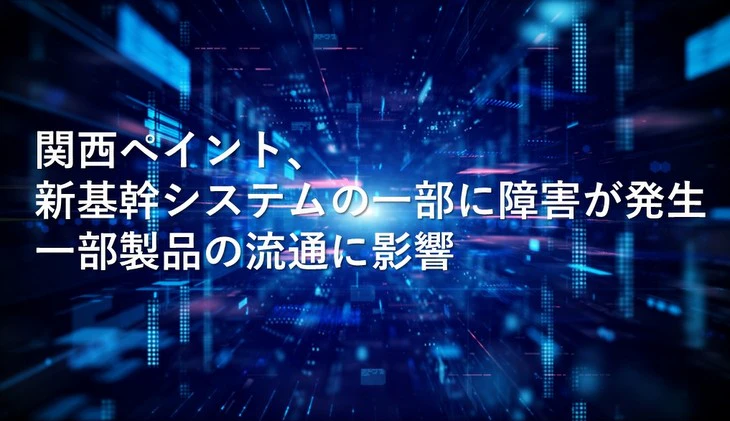
関西ペイント、新基幹システムの一部に障害が発生 一部製品の流通に影響
2026/01/23
-

タジマ、アプティと業務提携 出張整備マッチングと連携
2026/01/23
-

スズキ、新型「キャリイ」発売 外観刷新と安全機能拡充
2026/01/23
-
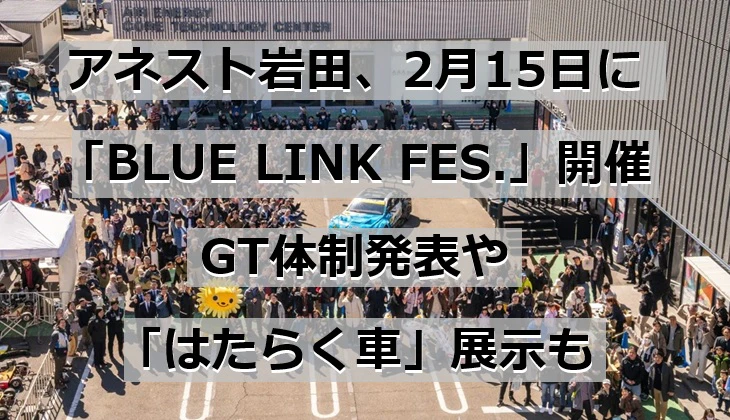
アネスト岩田、2月15日に「BLUE LINK FES.」開催 GT体制発表や「はたらく車」展示も
2026/01/22
-
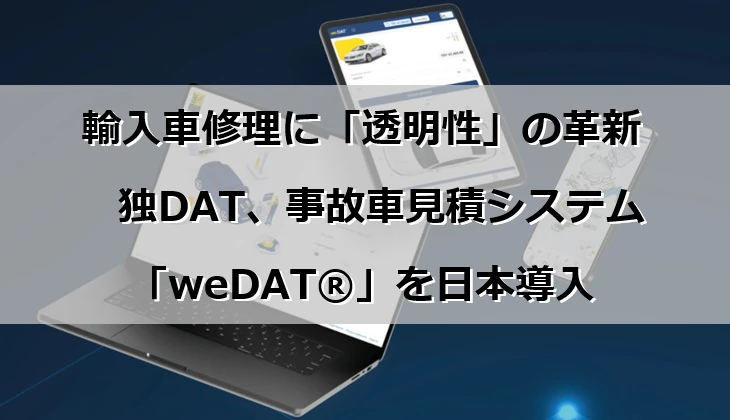
輸入車修理に「透明性」の革新 独DAT、事故車見積システム「weDAT®」を日本導入
2026/01/21