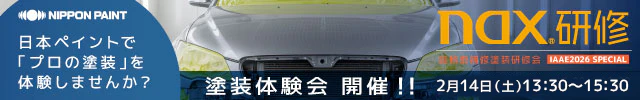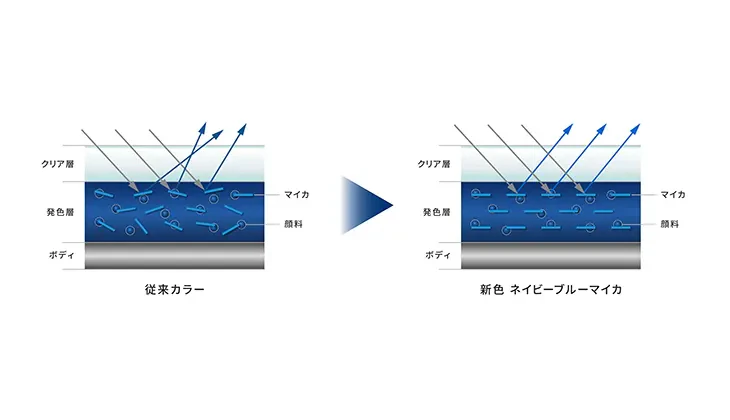JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
[連載]事例と解説ー整備業のための補助金活用講座
第6回 事例:EV対応型工場の増設
2025/09/10
今回は、自動車販売・整備を行うA社が、新分野展開に挑戦した事業再構築の事例をご紹介します。 A社は北陸・東海エリアで輸入車の正規ディーラーとして新車・中古車販売、整備、鈑金塗装、保険代理業などを展開し、30年以上にわたり黒字経営を続けてきた老舗企業です。特に地元では輸入車ブランドを独占的に取り扱い、高いブランド力と地域密着型の運営体制によって厚い顧客基盤を築いてきました。また、特定整備認証を早期に取得し、OBD車検にも対応するなど、先進整備技術にも柔軟に対応しています。
一方で、電気自動車(EV)の普及加速という業界構造の変化に対しては課題を抱えていました。EVはガソリン車よりも車重が重く、既存の整備工場にあるリフトでは整備士の安全性が確保できず、また、EV特有の電装部品や駆動系に対応する整備機器も不十分でした。さらに、充電設備の整備も遅れており、生産性の低さが大きな問題となっていました。ガソリン車とEVの両立を図るには、両方に対応できる体制の構築が喫緊の課題でした。
A社が行ったSWOT分析によれば、強みは正規ディーラーとしてのブランド力、電子制御装置整備などの技術対応力、地域に根ざした広範な顧客網と地域貢献活動でした。一方、弱みはEV対応設備の不足と、それに伴う整備効率の低さでした。外部環境としては、政府によるEV促進策や市場の電動化傾向は大きな事業機会である一方、インフラ整備の遅れや人材不足、世界的な部品供給リスクが脅威として挙げられました。これらを総合的に判断し、EV対応体制の整備を次の一手として取り組むことを決断しました。
今回は事業再構築補助金(今年度は新事業進出補助金へ改名)を活用して、A社は既存工場に隣接してEV専用の整備工場を増築し、EV専用リフトやホイールアライメントシステム、急速充電器、普通充電器、キュービクル式高圧受電設備など、EV対応に不可欠な機器類を一式導入しました。整備士にはEV整備に必要な教育を施し、安全性と効率を両立した整備体制を構築。また、地元の専門学校と連携し、若手整備士の育成と将来の人材確保にも力を入れることとしました。
今回の設備投資総額は約1.5億円に及び、建築費が約1億円、整備・充電設備費に約5千万円を投入。これにより、EV販売から車検・整備・修理・保険までを一貫して提供可能な体制を整備し、従来のガソリン車事業との両立を図るとともに、将来的なBtoBビジネスの拡大も視野に入れています。
A社の取り組みは、電動化と整備技術の高度化という構造変化に対応する戦略的な挑戦であり、設備投資と人材育成を両輪に、持続可能な成長を志向した実践例です。既存資源を活かしながら新たな需要を掴みにいく姿勢は、今後の整備業界のあり方を考える上で大きな示唆を与えるものです。他の整備事業者にとっても、EV全盛時代への対応を検討する際の有力な参考事例となるでしょう。
次回も自動車アフター業界の事業者の次の一手をご紹介します。
バックナンバーはこちらから
筆者プロフィール

山田健一(株式会社フォーバル)
国内大手EC会社にてマーケティングを担当。その後、大手M&Aアドバイザリー会社にて上場企業の経営戦略立案やM&Aアドバイザーとして数多くのM&Aを実行支援。2016年に(株)フォーバルの事業承継支援事業立ち上げに参画。自動車アフターマーケットでの後継者問題の解決、補助金支援に力を入れている。
株式会社フォーバル https://forval-shoukei.jp/