 JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
BSR誌面連動企画『磨きの匠』 FILE #009 スリーエムジャパン・宮永健彦
“磨き”の前工程である下地及び塗装との関係性を意識する
2025/11/14
PROFILE
宮永 健彦(みやなが・たけひこ)
スリーエムジャパン
経験年数 30年
主な経歴 自動車整備専門学校卒業後、鈑金塗装工場で塗装技術者として勤務した後、塗料メーカーで調色技術研修などのトレーナーを担当。2010年よりスリーエムジャパンで鈑金作業から下地処理、塗装、磨き作業まで幅広い内容のトレーニングを担当。
座右の銘 “がんばりすぎない”

――下地~塗装の仕上がりと磨きの作業性・品質との関係性を意識
“磨き”と言うと、どうしてもポリッシング工程のみに意識が向きがちだが、補修塗装後の“磨き”においてはその前の工程である下地から塗装までを適切に進めておくことで、作業が非常に楽になる。下地処理では適切な番手のサンドペーパーで肌をしっかりと整え、塗装作業では適切な塗装環境の整備や塗料カップシステムなどの活用で、ゴミ・ブツの付着を最小限に抑える措置が求められる。
また、ブツ取り後の処理に3000番、5000番と高番手のサンドペーパーを用いることで、その後のポリッシング作業時間を短縮することができる。ポリッシング時間が短くなれば、摩擦による塗膜への過熱を抑えることができる。
磨き作業による摩擦で塗膜に熱が加わると、クリヤーが膨張してしまう。このクリヤーの膨張によって覆い隠された磨き傷は、そのままの状態でどれほど磨き続けても、取り除くことはできない。そして作業後に熱が逃げ、クリヤーの膨張が収まった時に、バフ目戻りなどの現象が生じてしまう。
また、塗膜が軟らかい自己修復タイプのクリヤーは、傷が入りにくく、一度傷が入ると取り除くことが難しいという性質を持つ。そのため、磨き作業においては“傷を入れ過ぎない” ことが非常に重要となる。高番手のサンドペーパーの利用で磨き作業時の発熱を抑えることは、自己修復タイプのクリヤーに対しても非常に有効な手段と言える。
――次世代を担う若手技術者へメッセージを
補修作業後の磨き作業には、塗装という前工程があり、塗装の前には下地工程がある。工程に前後があるからこそ、その関係性について筋道を立てて考える必要がある。前後の作業の関係性を意識すると、各作業がほかの作業に与える影響が見えてくる。その時に、自分の中で基準となるツールや作業工程を持っておくことが大事になる。一つの基準を持つことで、作業に迷った時にそこに立ち返ることができる。
当社は下地から磨きまでの各工程で製品を提供しているメーカーであるため、磨き作業における課題について前工程を含めた広い領域で検証し、サポートすることができる。何か困りごとがあれば、ぜひ気軽に相談してほしい。
※ボデーショップレポート 2025年12月号に掲載
【作業実演】
ランダムオービタルポリッシャーを用いたブツ取り後の磨き作業
ブツ取り後の研磨傷を高番手のサンドペーパーで処理した後、目消し工程からランダムオービタルポリッシャーを用いて2工程で仕上げる。
あなたにおすすめの記事
-
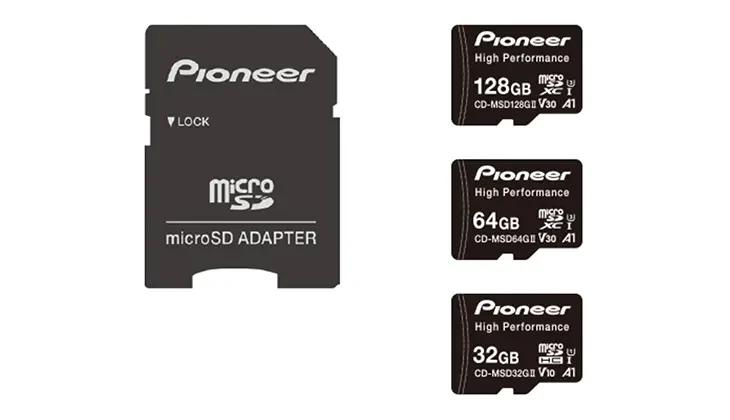
パイオニア ドライブレコーダー向けmicroSDカード「CD-MSD128G2」「CD-MSD64G2」「CD-MSD32G2」
2026/02/28
-

ホンダテクニカルカレッジ関西、「春の体験授業2026」を3月26・27日に開催
2026/02/27
-

オートバックス、キッザニア東京「カーライフサポートセンター」をリニューアル
2026/02/27
-

SKY GROUP、神奈川エリア初の「ランボルギーニ横浜サービスセンター」をオープン
2026/02/26
-

エムケー精工 間口2600mmのドライブスルー門型洗車機「リヴェールEX」
2026/02/26
-
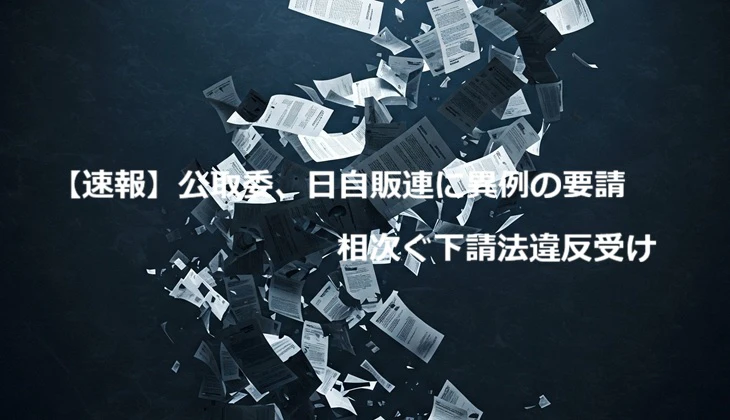
【速報】公取委、日自販連に異例の要請 相次ぐ下請法違反受け
2026/02/25


























