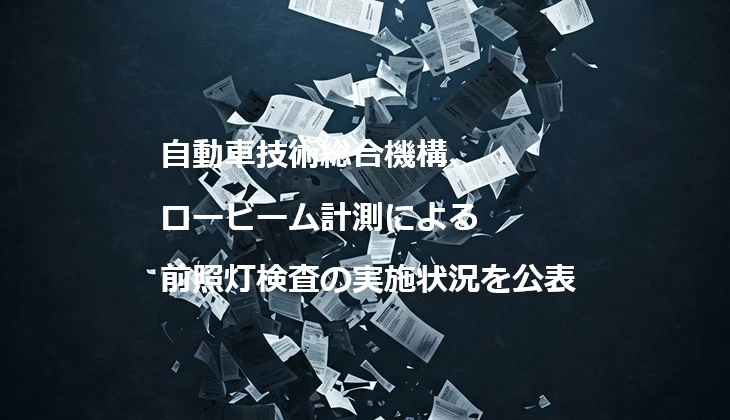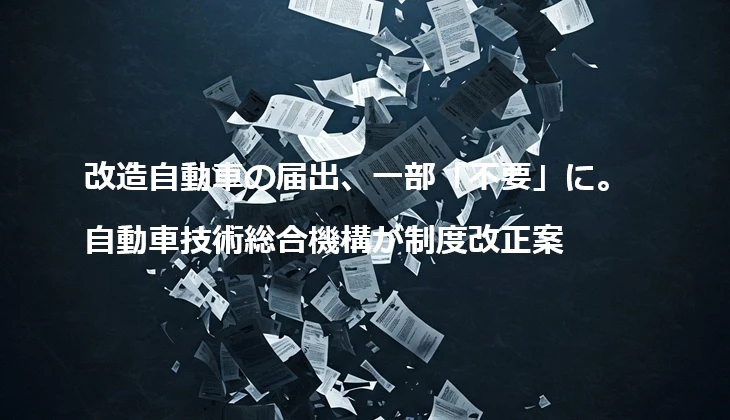JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
[特集]地域連携のススメ(7)~事例:ロータスTMパートナーズ(石川県七尾市)
大規模災害にも負けない整備工場の地域連携の必要性
2025/08/01
地域連携のモデルケースとでも言うべき、2018 年4月に設立された能登地区の全日本ロータス同友会加盟工場6 社の共同店舗となるロータスTMパートナーズ(高野憲治社長=北日本自動車)。能登半島を襲った巨大地震に対し、整備工場の地域連携はどのように活かされたのか。理事を務めるエース自動車・谷内政則社長に話を聞いた。また、TMコーポレーション・室谷眞一社長(=辰口自動車販売)に、整備工場の地域連携の必要性をたずねた。
地震をきっかけに結束が強まった能登地区6社連携事業
石川県能登地区のロータス加盟工場6 社が共同運営する店舗として、2018年4月にオープンしたロータスTMパートナーズ。24 時間365日営業ではないが、TMコーポレーションの事業モデルである保険を中心にしたトータルカーサービスを展開しており、加えてセルフ式ガソリンスタンドを併設し、ここを起点に新たな集客も図る。
ガバナンスを整え、運営会社6社からスタッフを出向させるなど、どこよりも早く整備工場の地域連携に取り組んできた。だが、2024年1月1日に発生した能登半島地震が様相を一変させる。
同店及び運営会社6 社は、幸いにも地震による甚大な被害は避けられ、事業を継続できている。しかし、地震をきっかけに能登の地を離れていく住民が後を絶たず、「地震発生前後で人口が15~20%減少した。加えて高齢化も進んでおり、人材不足が深刻な問題となっている」(谷内氏)。それは各社のスタッフも同様で、数人がやむを得ない事情で会社を去っていった。
だが、この地震を機に運営会社6 社の結束は強まった。これまで車検・整備は各社で対応するケースが目立ったが、人手不足により各社は受け付けだけを行い、車両を同店に持ち込むオペレーションを採用。現在、月間約30 台を同店で処理する。「これまで共同店舗を充分に活かしきれていなかったのは否めないが、ようやく発足当初に描いていた協業体制の姿が形になりつつある」。
地震発生から1 年半が経過したが、いまだ復興は道半ば。だからこそ、6社が手を取り合うことで地域生活を支え、能登地区の復興を後押しする。
地域連携の成否はガバナンスの構築
能登地区の6社連携を推進し、同店の取締役にも名前を連ねる室谷眞一社長は、整備工場の地域連携の必要性を訴える。「もはや1社で生き残れる時代ではなくなった。個社ごとの強みと弱みを補い合い、地域住民の生活を支える整備工場間の連携が不可欠だろう」。
その成否の鍵を握るのはガバナンスの構築。「自社のスタッフを共同店舗に出向させるのは、口で言うほど簡単ではない」。出向したスタッフに不利益が生じないように、各社各様だった給与は一番高い会社をベースに基準を設け、また勤務形態や通勤時間の変更なども考慮した就業規則を策定した。また資産となる設備機器は、設備ごとに各社が負担する形を採用した。「同業者だからこそガバナンスが最も大事。またパワーバランスも重要で、決して元請け・下請けの関係性ではないことを理解してほしい」と強調する。
能登半島地震を経験し、「大規模災害は廃業のトリガーになり得る」。特に、少子高齢化が進む地方こそ万が一に備え、早期に地域連携のスキームを整える必要があるだろう。

![[特集]地域連携のススメ(7)~事例:ロータスTMパートナーズ(石川県七尾市)](https://images.microcms-assets.io/assets/d2e4fe1647df4cbaa78dfa610b1ed1a4/c844ca8be6174e098e3aca8ec80e8037/feature_rotusTMp_02.webp)