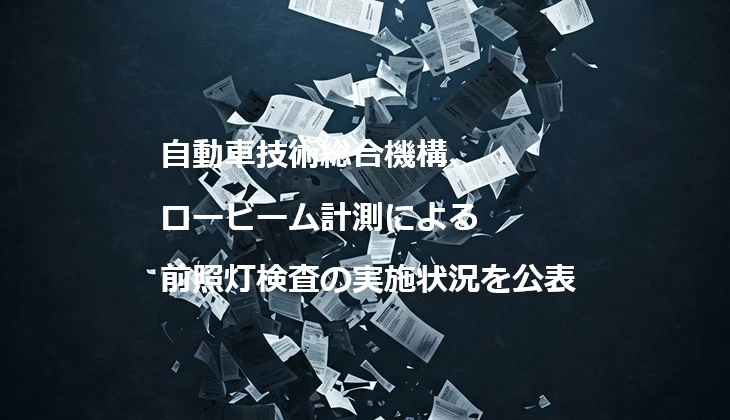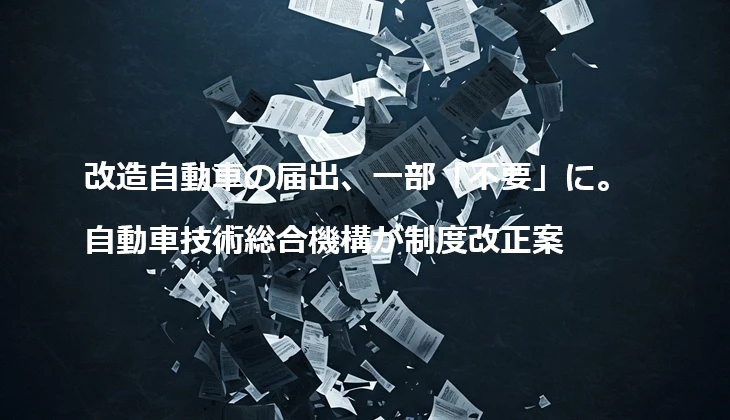JOURNAL 最新ニュース
JOURNAL 最新ニュース
[特集]地域連携のススメ(6)~事例:琴浦モビリティグループ(コトモビ)
琴浦町の整備事業者5社による 「ゆるい連携」でつながる「コトモビ」
2025/08/01
人口1万5,642人、高齢化率38.9%(2025年5月時点)。鳥取県中部に位置する琴浦町は、過疎化が進む地域である。将来的な整備難民の懸念に加え、整備工場経営にも暗い影を落とす。そこで立ち上がったのが5社の専業整備工場である。「ゆるい連携」を合言葉に、地域連携を実践するコトモビは2025年7月に結成から5年を迎えた。本格的な地域連携を展開する全国でも唯一無二のコトモビが実現してきた成果と現在地を聞いた。
過疎の町に生まれた整備業の連携、コトモビ
鳥取県のほぼ中央に位置する琴浦町は日本海と大山ふもとの山間部で形成する風光明媚な町である。2004年に東伯町と赤碕町が合併して琴浦町となった。2010年当時、約1万8千人を抱えていた人口は年々減少し、2020年には1万6千人にまで減少した。ディーラーが撤退し、バスが廃止となり、交通インフラが脆弱になるとともに将来的な整備難民が出てくる懸念を、赤碕ダイハツの上田啓悟社長は、2010年代初頭より懸念していたという。また、いずれ団塊の世代が後期高齢者となり、「免許返納が増えていった時、町の人口と免許人口の減少は加速するだろう」と上田社長は予測した。
市場の縮小、交通インフラの衰退、自動車整備事業者の事業継続といった諸問題に対し、上田社長が出した答えは同業者による連携の道であった。しかしながら、連携の組織作りは簡単ではなかった。整備工場の団体やFCではなく、協同組合や協業組合でもない。このような新たなグループの形は整備業界に前例がなかった。気の合う同業の仲間を集め、連携の構想を語ったがその趣旨を理解してもらうために、相当に長い時間をかけたという。
地域に移住した若者がコトモビ推進の原動力に
「会社を乗っ取ろうとしているのでは?」という勘ぐりの声もあったという連携づくりの過程で、1つの転機になったのが、出﨑隆晟氏の入社である。広島の大学在学中の出﨑氏が、赤碕ダイハツで展開する格安のレンタカーでコペンを借りるため、琴浦町を訪問。町の人々との温かい交流に魅了され、大学卒業の翌月赤碕ダイハツに入社した。
「移住を決意したきっかけは、琴浦の人の温かさと優しさ」と出﨑氏。上田社長はその出﨑氏に地域連携アライアンスの事務局を担当してもらうことで、組織作りを急展開させた。
「事務局を作り、連絡事項についてワンクッション置くことで運営は円滑になった」(上田社長)という。また、コロナ禍の只中にあり、スタッフのウイルス感染で出社できない人材が社会問題になったことも連携の組織化を後押しした。こうして琴浦モビリティグループ、略称コトモビは2020年7月に正式に発足した。参加企業は赤碕ダイハツを中心に赤碕ホンダ販売、なにわ自動車、くらみつ自動車工業、そしてながれ自動車販売の5社で構成。事務局は既述の通り、赤碕ダイハツの出﨑氏が担当し、コトモビの会長に上田社長が就任した。「ゆるい連携」を合言葉にコトモビがスタートする。
協力・共有・分担が新たな自動車整備を切り拓く
コトモビの理念は「協力・共有・分担」である。5 社の休日をずらすことで、グループ内の店舗が必ず開いている体制を整えた。ロードサービスも含めて、自社が休みでもユーザーに安心していただくのが狙いである。とりわけ、日曜日の業務を各社当番制にしたことで、ユーザーの安心への配慮だけでなく、各社社員が日曜日に休めるようにもなった。
また片道1 時間かかる鳥取市内の運輸支局に出向く業務を定期便として一本化することで、時間とコストを大幅に削減した。この他、新車、中古車の車両販売の在庫共有、タイヤなどの仕入れ共有化で、安価な仕切りで連携パートナーに展開することも可能になっている。
さらには既述した感染症リスクにとどまらず、近年多発する災害リスクにも備えられるため事業者側、そしてユーザーにとっても安心が増したことは大きい。そうしたバックアップ体制に加え、人的、整備機器の共有など、連携は様々な方面に拡大している。
後継者問題から若手のつながりまで地域連携の化学変化
エイミングとガラス交換という電子制御装置整備はなにわ自動車が担当する。同社は浪花社長が起業し、個人で業務を担ってきたが、コトモビをきっかけに娘婿が入社、自動車ガラスの技術を習得し、新たな体制が整いつつある。これにより後継者問題も解消した。元々、琴浦町に自動車ガラス事業者がなかったため、今ではコトモビ以外でも自動車ガラス業務を受注し、業容を拡大させている。アライメントテスターをはじめ、エイミングの機器、自動車ガラスに関連する機材は補助金を利用して調達した。補助金申請のスペシャリトとの評価が高いながれ自動車社長がアドバイスを送り、補助金採択にこぎつけた。
上田社長は「コトモビのメリットは協力・共有・分担だが、それ以上に目に見えない効果が出てきている。後継者ができた会社をはじめ、連携する5社の若手社員が自然発生的につながって、結束を強めている」と、当初予想しなかった様々な化学変化が起きており、グループを活気づけているという。「コトモビ」発足当初から掲げてきた、仕事を楽しむというコトモビの趣旨が実践されている証である。
「我々には5年かけて作り上げてきた連携のアドバンテージがあり、これまでの整備業界では誰も見たことのない景色を見ていると自負している。今後、人口減少はさらに進むと考えられるし、また災害リスクも高まるだろう。切羽詰まった状況で、連携をスタートさせるのではもう遅い。連携の形は自由で、2社だけでもいい。連携が生む地域の活性化で、新たな人材を地域に呼び込むことができる。地域連携における真のメリットはそこにある。そして連携を成功させるにはゆるいつながりが重要だ」(上田社長)。





コトモビの具体的活動として折り込みチラシやTVCMなどで広報活動を展開。そのコストのみ、各社で負担する按分制でグループが運営されている。会費などは設けず、あくまでもゆるい連携が基本線。それがグループの発足から、今日に至るまで持続可能なグループ活動の原動力となっている。近年は協力企業のリサイクル業者に廃車を提供するリターンとして1 台につき1,000 円を受けることでグループ運営の資金に充てている。チラシには各社社長のプロフィールなどをイラストで分かりやすく掲載。これまであまり知られていなかった自動車屋さんを身近な存在に変えた。また、「コトモビ」というキャッチーな名称の効果も含めて、地域のモビリティ全般を請け負うグループとして年々知名度も上がっている。
![[特集]地域連携のススメ(6)~事例:琴浦モビリティグループ(コトモビ)](https://images.microcms-assets.io/assets/d2e4fe1647df4cbaa78dfa610b1ed1a4/d28c0f9143a14a4487374279e122dbc3/feature_kotomobi_06.webp)
![[特集]地域連携のススメ(6)~事例:琴浦モビリティグループ(コトモビ)](https://images.microcms-assets.io/assets/d2e4fe1647df4cbaa78dfa610b1ed1a4/956dd91f466147c1831d20285a19cc59/feature_kotomobi_07.webp)